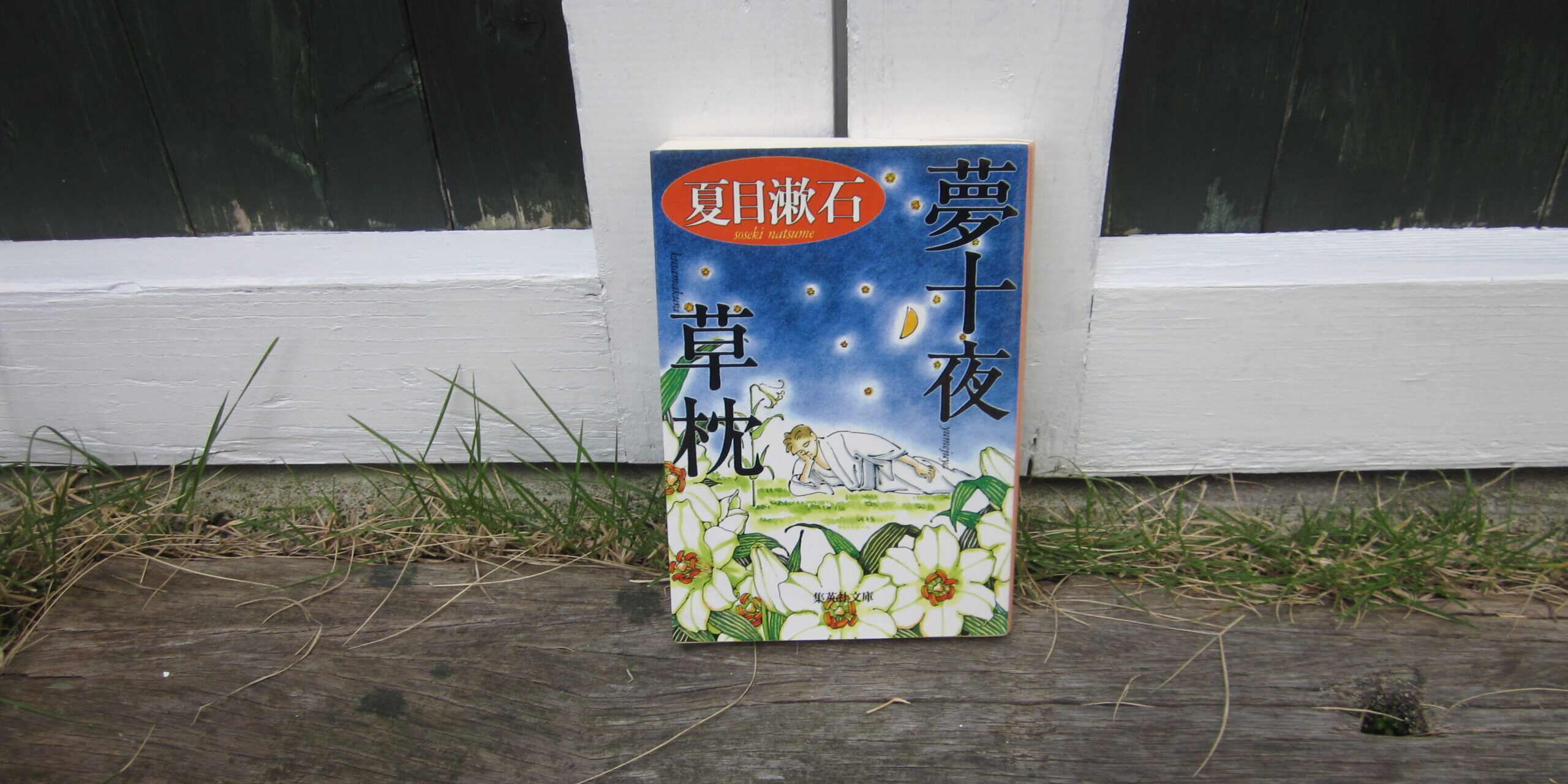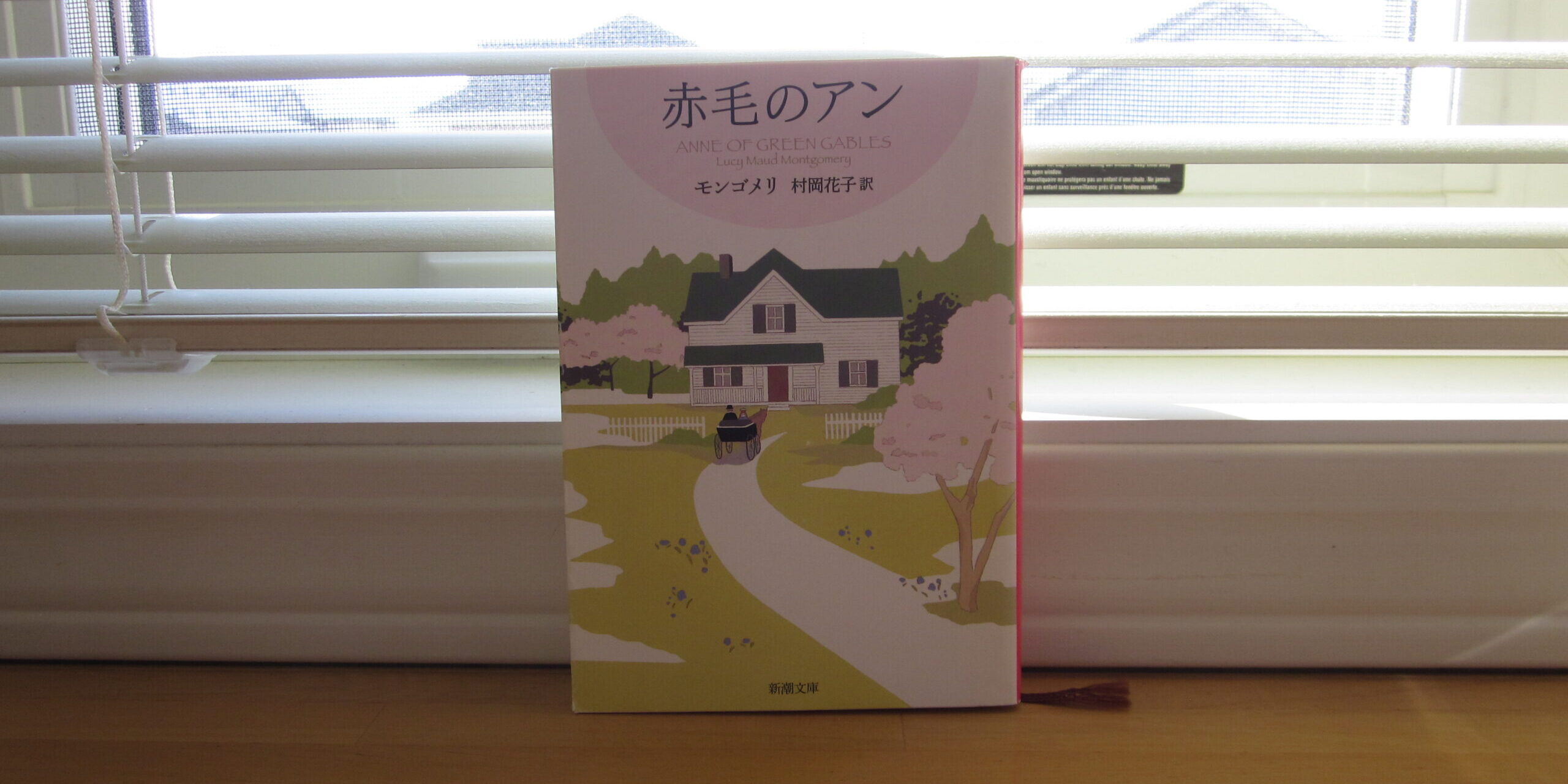小説、詩、エッセイ。どの形態をとっても、文章の書き出しは難しいものです。書き出し、あるいは最初の一文で、その文章に対する読み手の態度が大方決まってしまうと言っても差し支えないでしょう。この理由から、読み手を自分の文章の中に引きずり込みたいという思いが強ければ強いほど、ありとあらゆる文句を考えても満足することができずに思い悩むことになるわけです。私は仕事柄、総合型選抜による大学受験を考えている生徒の小論文を指導する機会があります。生徒たちの様子を見ていると、受験する大学が具体的になるにしたがって、小論文の書き方を学ぼうとする態度にも熱が入ります。可能な限り合格に近い小論文を書こうとすると、やはり書き出しの文章に思い悩むようです。いざ書き出してしまえば、そのあとは意外とするすると小論文を書き進めることができる場合が多く見受けられます。それだけ文章の書き出しが作品そのものに与える影響が大きいということになります。
書き出しの文章のうち最も有名なものの一つが夏目漱石の『草枕』であり、古典に題材を求めれば『平家物語』ということになるのかもしれません。これらの作品の書き出しは学校教育の中で暗唱させられるか、あるいはその素晴らしさゆえに誰の心にも残りやすいものです。私がその秀逸さにうならされた作品の一つに、池田満寿夫の『エーゲ海に捧ぐ』(昭和52年上半期、第77回芥川賞受賞)があります。その書き出しの一文は次の通りです。
アニタの足の裏に一匹の蠅が留まっている。
文章全体の中で書き出しが果たすべき最大の役割は、読者に続きを読み進めたいと思わせることができるかどうかにあります。上記の書き出しを読んで、皆さんはどう思うでしょうか。私は無意識のうちに続きの文章に食いつかされていました。足の裏に蠅が留まっているということは、アニタという名の女性はどこかに横たわっているはずです。眠っているのかもしれません。仮に眠っているのだとしたら、蠅が足の裏を這いずり回っても目を覚まさないほど深い眠りの中に沈んでいるのでしょう。いやもしかしたら、アニタはすでに死んでしまっているのかもしれません。アニタの遺体を目の前にした主人公が、アニタの足の裏に蠅が留まっている様子を目の当たりにして、改めてアニタの死に気づかされている場面を描いているのではないでしょうか。そう思えるのは、遺体と蠅にはどこか通底するイメージがあるからです。いずれにしてもこの書き出しの一文は、読み手である私に様々な想像の余地を与えてくれています。私はその答えが欲しくて、引きずり込まれるように文章を読み進めていってしまうのです。
わたくしといふ現象は 仮定された有機交流電燈の ひとつの青い照明です
これが宮沢賢治の『心象スケッチ 春と修羅』の序、すなわち詩集全体の書き出しにあたる文章です。どんなものであれ、文章はその読み手に自由な想像や発想の余地を与える力を秘めています。私がこの文章に初めて接したのは小学生のころですが、それ以来、この文章を読み返すたびに今も変わらず同じ「想像の景色」の中に放り込まれます。私という存在は、自然界における一つの現象にすぎません。自然の営み全体から見れば、ごく些細な存在でしかないのです。しかし、そこに恐れはありません。自然は私が物質的に生きていても死んでいても、いつでも優しく包みこんでくれていることに変わりはないからです。私がそんな思考の中に思い描く「想像の景色」とは、暗闇の中にどこまでも落ちていく私が誰の目にも見えなくなる瞬間、ふわりと青い光を放つという光景です。私という存在は取るに足りないちっぽけなものです。しかし小さいけれども青い光を放つことができます。一つの青い照明として、誰かの足元を照らす光になることができればそれでいいのではないか。『春と修羅』の書き出しの文章は、そんな私の存在を最後のところで肯定的に受け止めることを許してくれているのです。そしてもっともっと自分を肯定してもらいたくて、私は賢治が紡ぐ言葉の糸を辿り続けてしまうのです。
17.『新編宮沢賢治詩集』 天沢退二郎編 新潮社文庫 平成16年3月25日29刷
 書評
書評