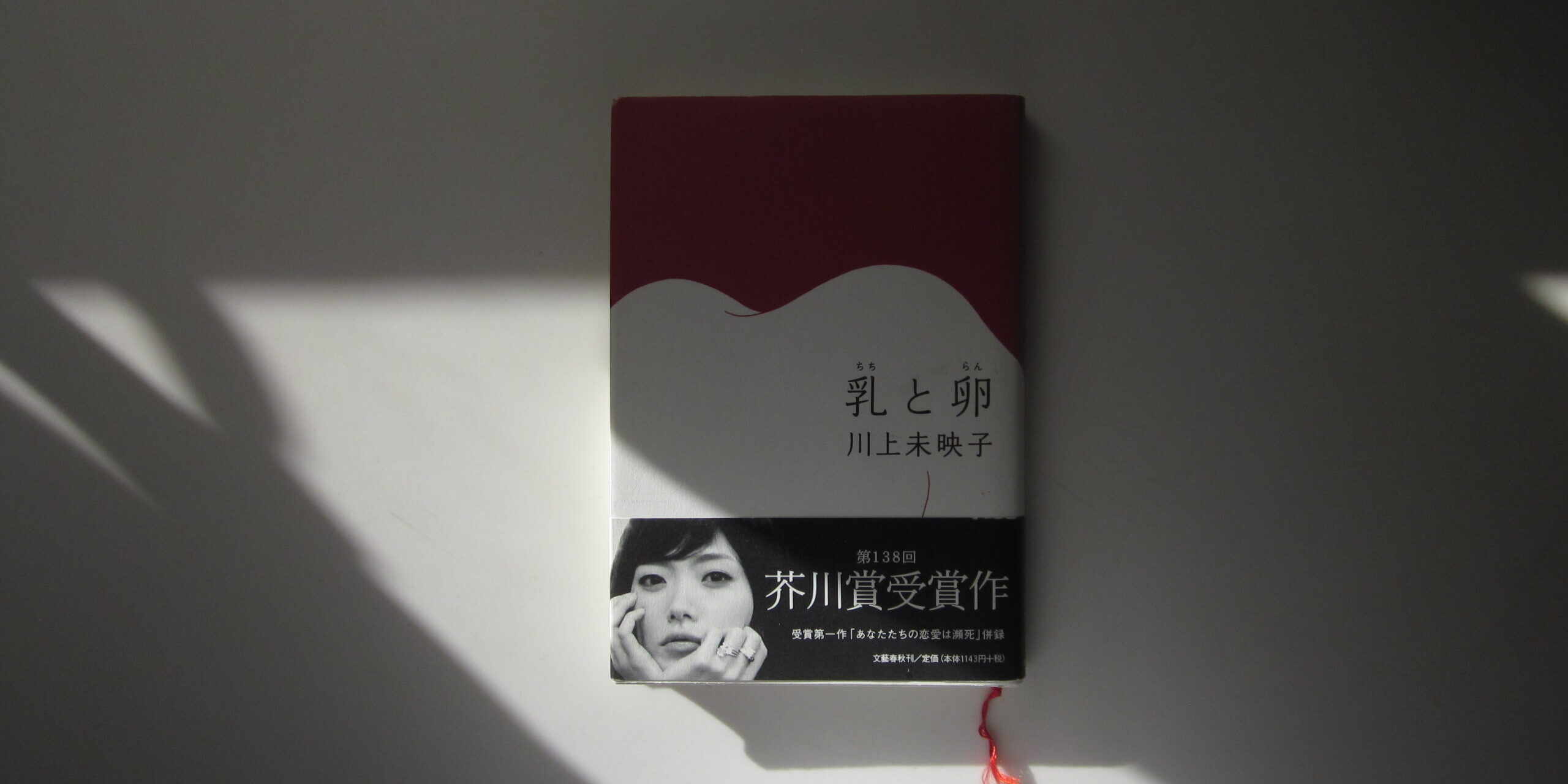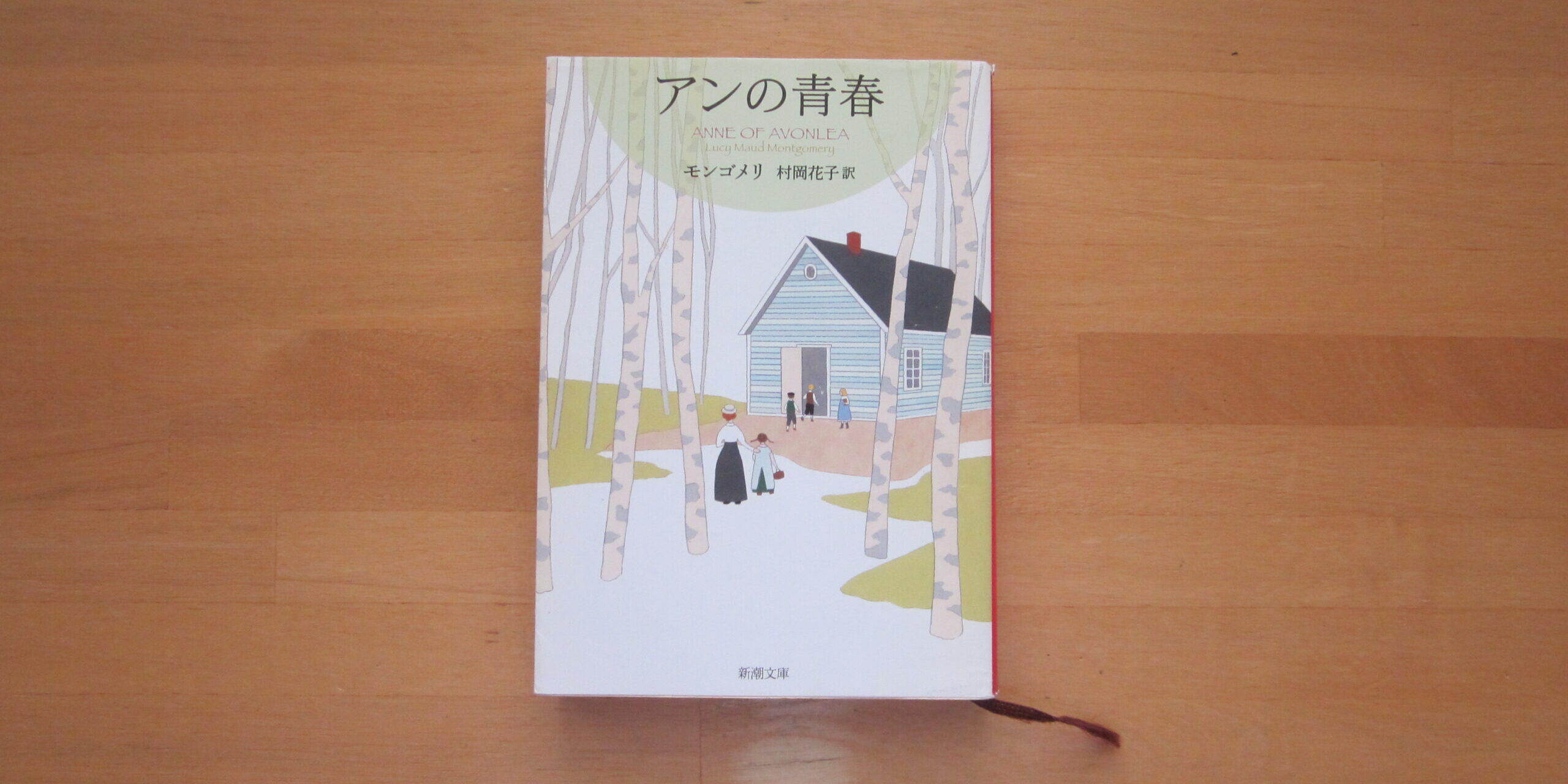私は一般化や類型化を好みません。特に芸術に関しては、個別性や特性を見出してこそ作品を楽しむことができると信じています。敢えて芸術に限定したのには訳があります。ある作品が、他の作品と異なる特性を有しているからこそ受け入れられる、評価されるという側面を、各分野の芸術こそがより強く持ち合わせていると考えるからです。傾向や類似点を見出して、その作品の作者が受けたであろう影響の系譜をたどり、作品の源泉を掘り起こそうとする手法が評論の世界では多く用いられます。的を射た評論はそれそのものが作品としての高い品格をもち、示唆に富んでいます。しかしそれはそれとして、音楽も絵画も、あるいは陶磁器や映画も、その作品がもつ特性がとりわけ自分の内面に迫ってくるという現実に、皆さんは直面したことはないでしょうか。私にはそんな経験があります。だからこそ、個々の芸術作品の特性にこそ着目すべきだと考えるのです。それは2009年10月初旬のことでした。私は仕事でカナダのバンクーバーに滞在していました。その日の午後の予定がひとつキャンセルとなり、時間がぽっかりと空きました。街なかで空いた時間を埋めるため、何気なく入ることにした場所がバンクーバー美術館でした。
それまで、私は抽象画の価値に共感することができずにいました。抽象画という括りから作品を見ること自体、私が嫌う一般化や類型化に囚われたものの見方をしているということになります。敢えて一般化や類型化を避けて言うなれば、抽象的な概念の抽出を試みた作品の中で、心を奪われるような個体にはいまだに出合っていないということになるのかもしれません。そんな私が、ある作品に出合いました。その作品にまみえた瞬間、私の体に走ったある種の衝撃を今でも忘れることができません。ある媒体を用いた芸術作品を、その他の媒体を用いて同じように表現し直すことは基本的に不可能です。この場合は油絵具で描かれた作品を、言葉によって正確に再現することはできないという意味です。この事実を敢えて押し返し、さらに曖昧な記憶を掘り起こしつつ、言葉を用いて伝えようとする無謀をご承知置きください。その作品は50号のPサイズ(縦1167㎜×横803㎜)程の大きさだったと記憶しています。キャンバス全体が一面、濃緑色で塗りつぶされています。単色ではありますが、その濃淡が画面全体に絶妙な陰影を刻んでいます。その陰影が、人間の感情の起伏をごく自然に、しかも正確に表現しているように思えます。そして、その一面の緑の中央よりわずか上にただ一点、ささやかな黄色がほんのひと刷毛、これ以外には有り得ないという色と形と大きさ、さらには醸し出す雰囲気で佇んでいるのです。一目見ただけならば誰にでも描けそうな、単純な構図の作品だと思われてしまいそうです。しかし、その作品は私に理由すら悟らせないまま、私の胸の奥に直接入りこんでくる力をもっていました。その温かさや切なさは、もう言葉で表現することができる限界を超えています。今でも、文章を書いているこの瞬間にも、思い出しただけで同じレベルの感動が私のすべてを支配するほど、この絵のもつ力は私にとってとてつもなく大きなものでした。作者は分かりません。もちろん作品のそばに作品名と一緒に作者名も掲げられてはいましたが、覚えることができませんでした。しかしその作品名は鮮明に覚えています。『KISS』です。
『あられもない祈り』は、私にこの絵の存在を再び想い起させてくれました。言葉にするのが難しい感情を、登場人物の在り方に沿って真摯に表現してくれているように思えたのです。言葉の使い方が単に巧みだというのではありません。もどかしさや「分からなさ」を抱えながらも、何とか言葉を紡ごうとする登場人物を物語の中にきちんと立たせている、そんな印象を受けるのです。「一番苦しいのは、ねじれの部分なんです。心と体のどちらを信じればいいのか分からなくて、だから、自分のことも信じられない」「あなたに全身を見張られて与えられることで、幼い頃から他人の顔色ばかりうかがって、親や恋人と円満な関係を築くために感情を沈黙させて手首を切ったりすることすらいとわなかった私は生まれて初めて、自分に備わった両手や髪の先、背中や腰の骨一本までもが自分のものであることを実感した」「あなたは私の中の海をさらっていってしまった」といった具合です。ともすれば「うれしい」「悲しい」など、喜怒哀楽の単調な言葉を用いてしまいそうな場面を丁寧に描き込もうとする感覚が随所にちりばめられ、作者がその筆力を十分に発揮してくれているように思えます。また、逆説的な表現を用いて真理を突くような言葉にも感心させられました。「それが大きすぎる不安だからと、あのときは気付かなかった。あなたは弱い分だけ強情で、強い分だけ脆かったのだと」というように。もどかしさや「分からなさは」、『KISS』の背景の濃緑色を想起させます。逆説的な表現については、一般的には唇を思わせる箇所に赤を用いるところ、敢えて黄色で表現した点に類似しています。背景の濃緑色にしても唇を思わせる黄色にしても、『KISS』が現象ではなく感情によってなされた業であることが想起されます。『あられもない祈り』は『KISS』と同等の価値を私に見せることで、『KISS』と出会った瞬間の感動を私に想い起させてくれたのです。
私たち人間の感情は実に複雑な構造をもち、時として理解に苦しむ過程を経て現実の世界に表出されます。その表出、あるいは表現の仕方には様々な方法があり、各芸術は、それぞれの方法をもって役割の一端を担っています。『あられもない祈り』は、小説という芸術の価値の大きさを私に再認識させてくれました。小説家は、本来言葉では表しにくい感情をその筆力をもって巧みに代弁してくれます。そのことによって、読者である私たちは自らの感情に名前をつけ、納得することができるのです。あるいは登場人物を通して、自身の姿を省みる機会を与えてくれているという言い方ができるかもしれません。いずれにしても、私たちが小説や絵画をはじめとした芸術に触れる価値には、自分の姿を省みるという意味が込められていると思うのです。しかしその一方で、すべての小説や絵画が個人に対して同じ価値をもって迫って来るとは限りません。むしろ個人の内面をえぐり出し、取り出されたものと引き換えに体内に埋めこまれるほどの「動揺」をもって、真に迫ってくる作品に出合えることは実に稀です。そこには作品がもつ力はもとより、受け入れる側にも力が必要とされるからです。私には偶然にも『KISS』と、それと同等の重さをもって迫ってくる『あられもない祈り』出合うことが許されました。一般化や類型化をものともせず、絶対的な価値をもって迫ってくるこれらの作品に向き合うことができた事実は、何ものにも代えがたい幸運として私にもたらされました。そんな幸運の訪れをただ待つのではなく、自らの手で取りに行くことができるように、普段から力を蓄えることができる自分でいられることを、切に願ってやみません。
37.『あられもない祈り』 島本理生著 河出書房新社 2010年6月6日3刷
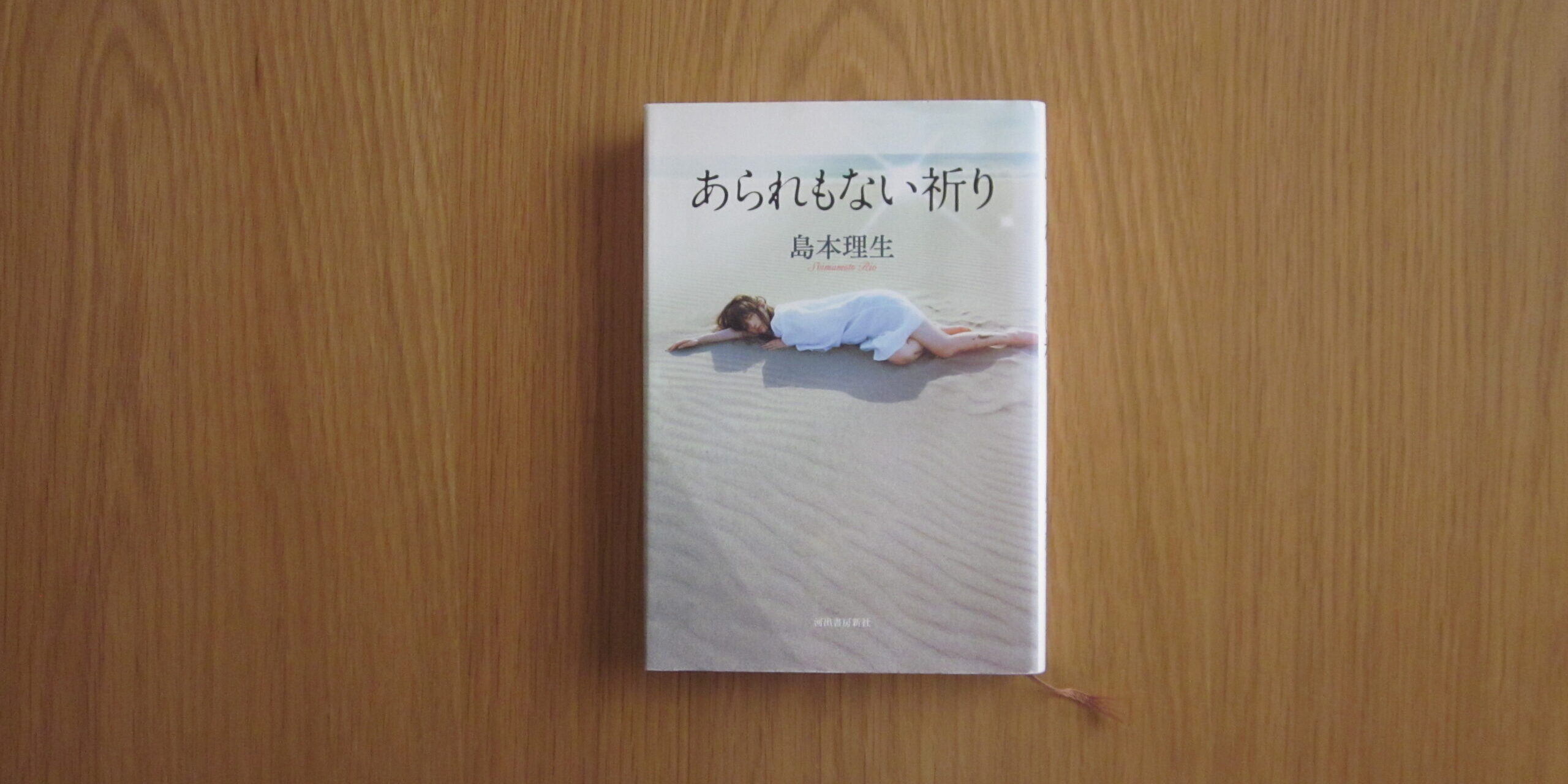 書評
書評