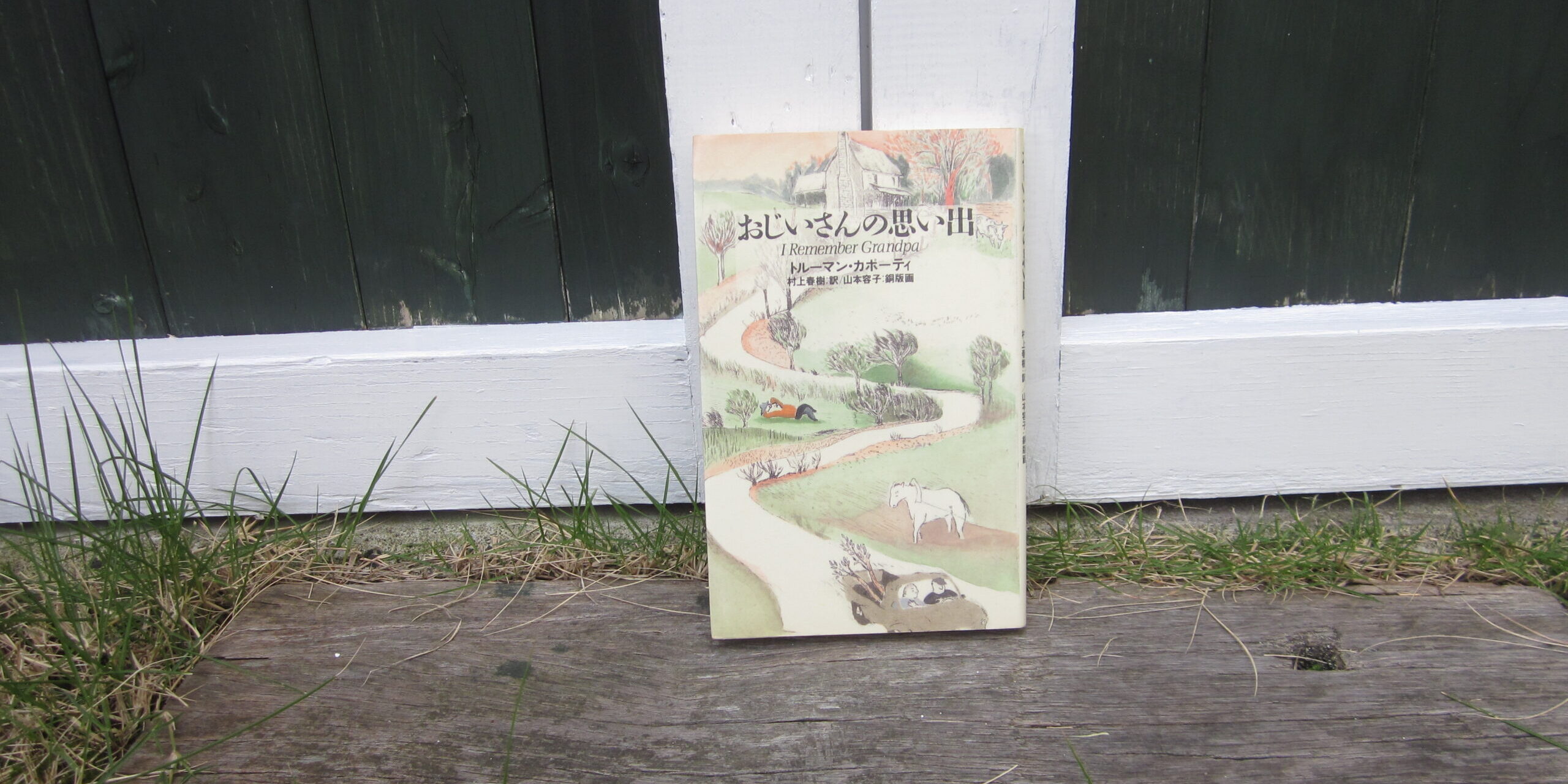夏目漱石の作品に関する研究成果は膨大な数にのぼります。そのため、ある作品についてどのような論考が成されているのかを調べるだけでも、相当の労力を要します。大学の文学部に属する学生が書いたものや、趣味で論考を手掛けている方々の記述まで合わせると、それこそ枚挙にいとまがありません。その中でも『夢十夜』は比較的論考が少ないものとされているようですが、それでもやはり様々な考察が試みられているようです。夢として語られる十の物語は、果たして漱石が見た夢にまつわるものであろうか。はたまた、漱石が見た夢であるとして、心理学的にはどのような意味をもつと考えられるだろうか、などなど、論考の視点や切り口だけでも数多く存在します。これらの事実から言えるのは、漱石の作品がどれをとっても我々の興味をかき立てるものであり、「夢十夜」もまた、漱石の作品として読み手の心を揺さぶる力をもっているということです。
十の物語の中でもとりわけ人々の興味をひく、不思議な物語として取りざたされるのが「第三夜」です。幻想的で現実感の乏しい設定の中にも、自分の身にもいつか同じことが起こりうるのではないかという不安を読み手に植えつける力を秘めているため、その文章の巧みさに思わず引き込まれてしまいます。ぜひとも実際の文章を読んで、物語の世界に接してもらいたいものです。私個人が十の物語の中で最も心惹かれるのは、「第一夜」です。「こんな夢を見た。(改行)腕組をして枕元に座っていると、仰向に寝た女が、静かな声でもう死にますと言う」という書き出しで語られるこの物語は、初めて読んだときから何度読み返してみても、私の胸を強く掴んで離さない力をもっています。私にとってこの作品がそんな力を発揮する理由はどこにあるのか。実はあまり分析好きではない私は、この疑念をずっと放っておいていました。しかし最近この物語を読み返したときに、ふとある考えが腑に落ちたのです。それはこの作品が、文字を可視化する力をもっているという考えです。
例えば「女」の描写について。「真っ白な頬の底に温かい血の色がほどよく差して、唇の色はむろん赤い」と書かれると、女の肌がただ白いのではなく、血の色が透けて見えるほどに儚い白さをたたえているのだというその光景が、息苦しいほどの静謐を伴って目の前に浮かんでくるではありませんか。また、「真っ白な百合が鼻の先で骨に徹えるほど匂った」との記述からは、白い百合となって再び男の前に姿を現したであろう女の存在自体を、男が体の奥底から欲していたことが痛いほど伝わってくるのです。「真っ白な頬」と「真っ白な百合」の組み合わせから、女の死後に男の目の前に現れた百合が、女の象徴として描かれている点はあまりにも明白に過ぎるかもしれません。しかし、明確な色彩を伴った文字の可視化が、読み手である私たちの心を一層作品世界に溺れさせる力を発揮している事実は変わりようがありません。
星の数ほどもある作家論や作品論の中には、それ自体が示唆に富み、機知に優れているものがたくさんあります。それを読むことによって今まで知らなかった新たな事実に気づかされ、読み手自身を豊かに深めてくれるものも少なくありません。そのような論考に触れることは、私たち読み手にとって楽しいものです。しかし、作品そのものの輝きに触れることはさらに重要です。『夢十夜』は、読み手にとってはとても難しい作品です。幻想的な分、行間に読み手の想像力が強く要求され、場合によってはうまくそれを埋める読み方ができない場合があると思うからです。私にも決してうまく行間を埋める読み方ができているとは思えませんが、「第一夜」の中に込められた文字を可視化する力をうまく利用すれば、この作品の素晴らしさにきっと気がついてもらえるはずです。もちろん、これは我々読み手の力もさることながら、作者である漱石の筆力に頼るところが大きいものです。どうかその筆力に上手く乗っかって、「第一夜」に描かれた場面の一つひとつを詳細に思い描きながら文字を追いかけてみてください。「遠い空を見たら、暁の星がたった一つ瞬いていた」の記述に、あなた自身の記憶に眠る暁の星の姿を重ね合わせることができるはずです。
16.『夢十夜・草枕』「夢十夜」 夏目漱石著 集英社文庫 2009年8月8日第15刷
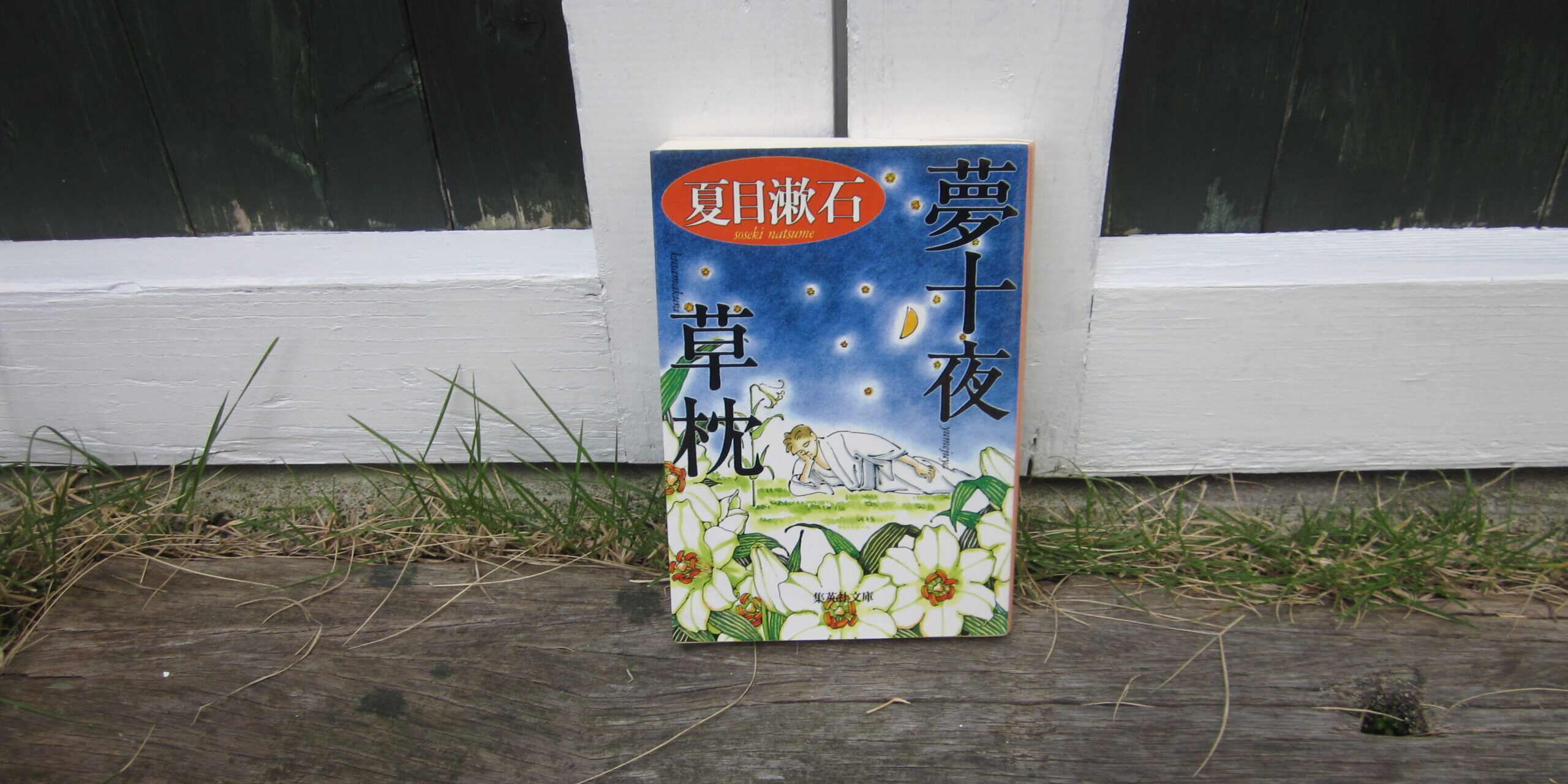 書評
書評