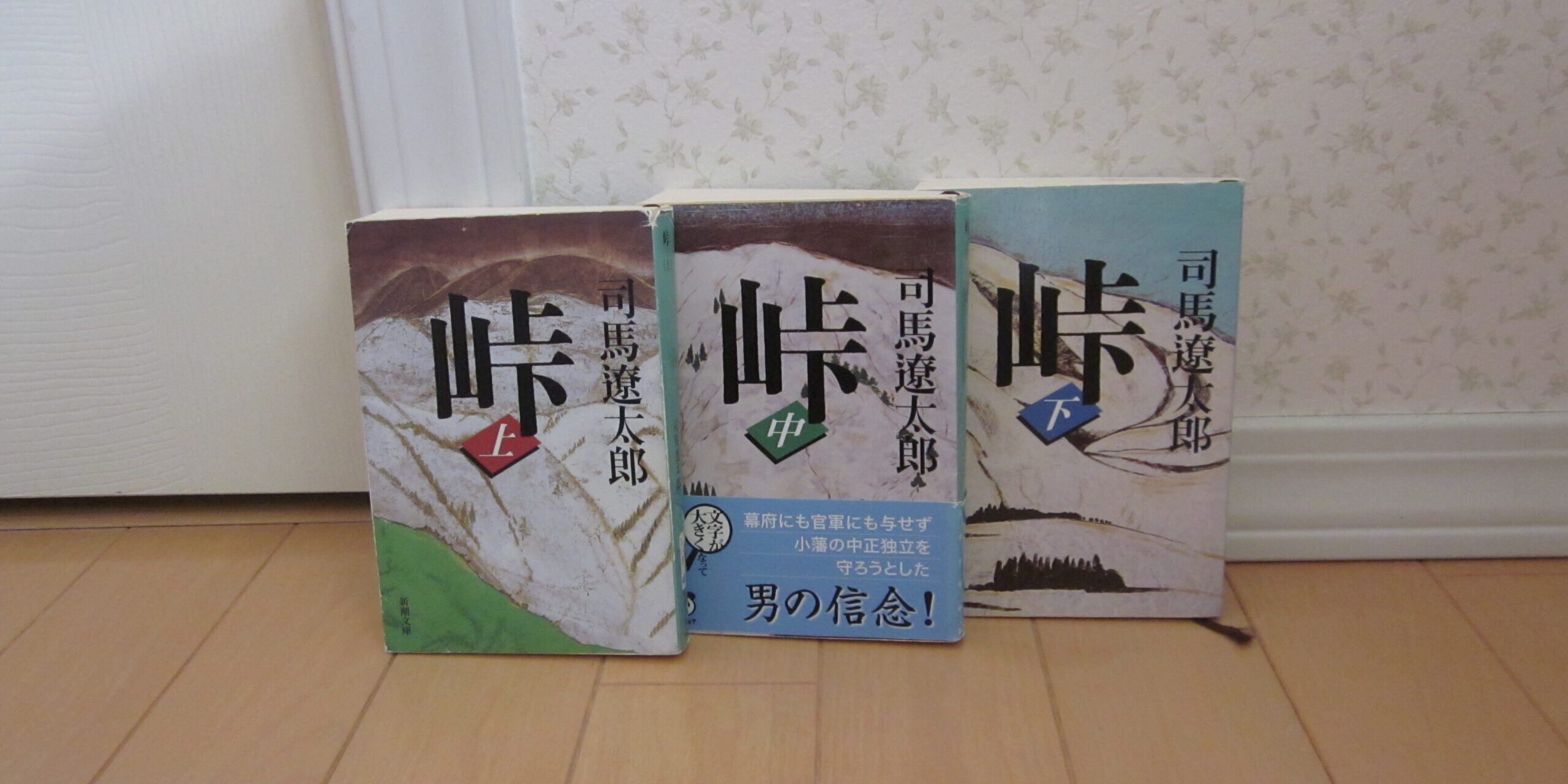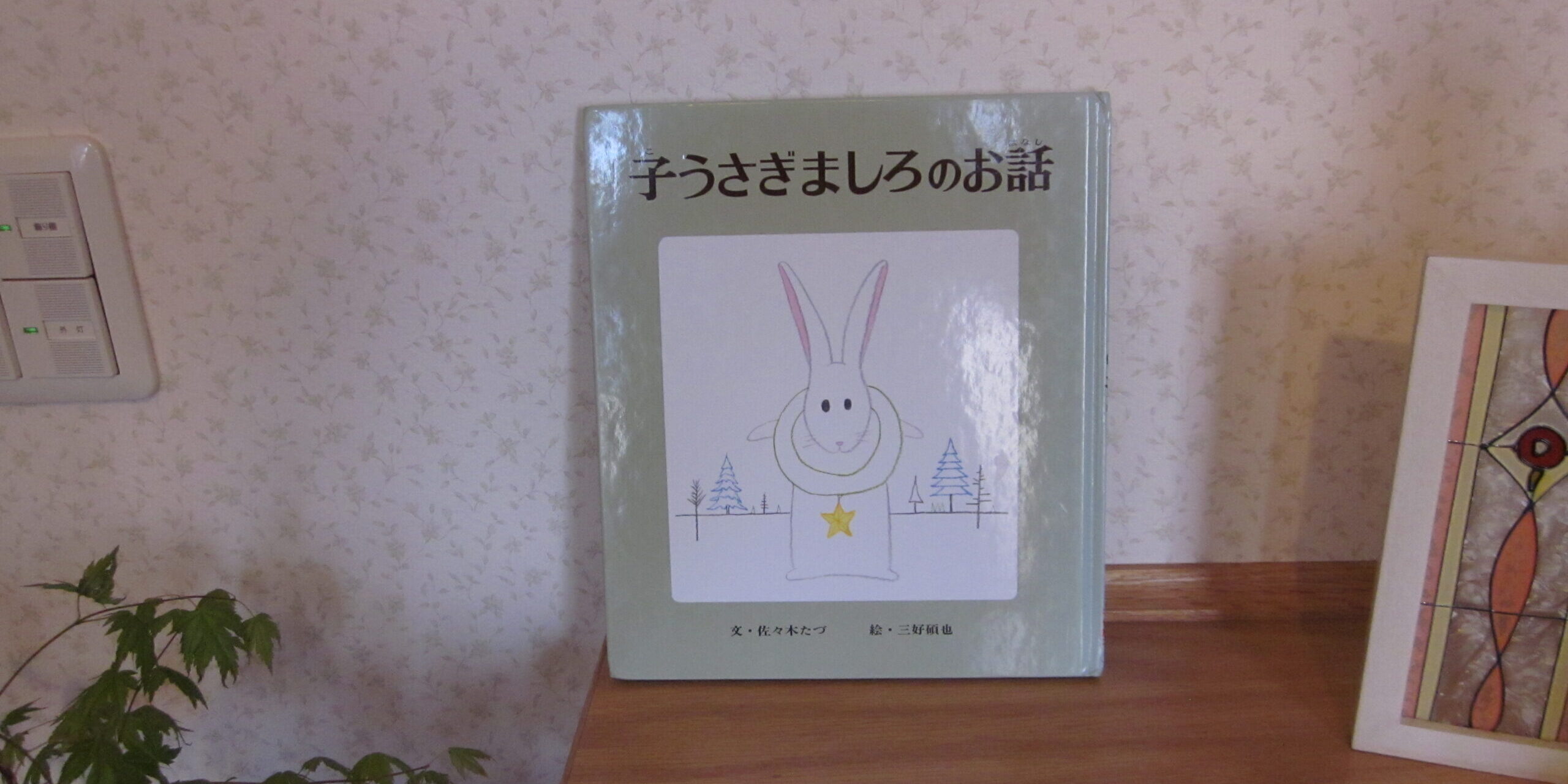人が寄り集まって話をする際、会話が盛り上がる話題のひとつに怪談や霊的体験談があります。日々の生活には喜怒哀楽がつきものですが、不可思議なものに対する恐れもまた、私たちの心を揺さぶる感情のうちのひとつです。この恐怖心に対するアプローチとして、怪談や霊的体験談ほど手近なものはありません。それは誰かの体験談として、伝聞の形で語られても通用するものですし、場合によってはテレビや雑誌で取り上げられた話でも、十分に人を引き付けることが出来るものです。自分自身の体験談として語ってしまうと、かえって信憑性が疑われる場合があるかもしれません。私の場合は霊的体験そのものがないので、体験を語ろうにも語れません。この理由から、怪談や霊的体験談については主に聞き役に徹するのが常です。しかし、信じるか信じないかは別にしても、人に営みのなかに、人の理解を超えた現象が有り得ることは十分に考えられることだと思っています。
『中陰の花』には、おがみやと呼ばれるウメさんが登場したり、主人公自身の不思議な体験が語られたりと、随所に霊的体験談が散りばめられています。ウメさんには予知能力というのか、仏教において神通力と呼ばれる不思議な能力があって、遠くから近くから、人々によって様々な悩み事が持ちこまれていました。しかしこれらの話題は、この物語を怪談や霊的体験談のレベルに留めるものでは決してありません。霊的体験をひとつの材料として、もっと大切な人間の精神性やいたわりが語られているのです。主人公の妻、圭子には、かつて流産した経験があります。この経験は、言葉にはしなくとも恵子の心に深い傷を残しています。しかし普段の明るい言動の中に、彼女がその深刻さを見せることはありません。そのため圭子の夫であり物語の語り手でもある僧侶の則道は、圭子のなかにある悩みの大きさに気がつくことができずにいます。そうかといって、この問題に関して則道が無頓着であるわけではありません。則道自身の心の中にも、父親としての責任を果たせず、授かった命を潰えさせてしまったことに対する後悔が深く根を張っています。圭子と則道は同じ感情を抱いて苦しんでいるはずなのに、お互いにそれを共有することが出来ないでいるところにこの物語の奥行きがあります。
圭子は、一人暮らしのウメさんのもとに、時折頂き物を持って行っていました。則道はそのことを知らずにいたのですが、圭子はウメさんのもとを訪ねるたびに「体の力抜きや」と声をかけてもらっていたことを話します。何気なく思えるこの一言が、実はとても思い遣りに満ちたものであることに気がついて、圭子はいつも温かいものを感じることができていたのです。ウメさんには予知能力が備わっていましたが、圭子に対してそのような力を使うことは決してなく、ただ静かに励まし続けていたのです。それを圭子は「祈り」ととらえます。「見えるとか見えないとかとちごて、ただ祈ってくれてたんやと思う」という一言に、その解釈が許されます。
人はそれぞれがどんな力を持っていようと、人に対する思い遣りを持つことで人たり得るのです。圭子と則道の間には、夫婦としての確固たる信頼関係があります。その信頼関係の上にもうひとつ、相手を思い遣る気持ちを付け足せば、もっと素晴らしい関係を構築することが出来ると思うのです。生まれてくる前に失ってしまった子どもに対し、お互いにどんなことを考えているのか、感情をぶつけあうことが出来ていれば、もっと早く深く、それぞれの苦しみを取り除くことが出来たはずです。この物語に「祈り」として描かれた感情を「思い遣り」ととらえた上での話ですが、特別な能力があってもなくても、他者に対して自分なりの思いやりを持って接することはできるはずですし、そうすることこそが大切なのです。『中陰の花』は、私にこのことを教えてくれました。
30.『中陰の花』 玄侑宗久著 文藝春秋 平成20年3月1日第15刷
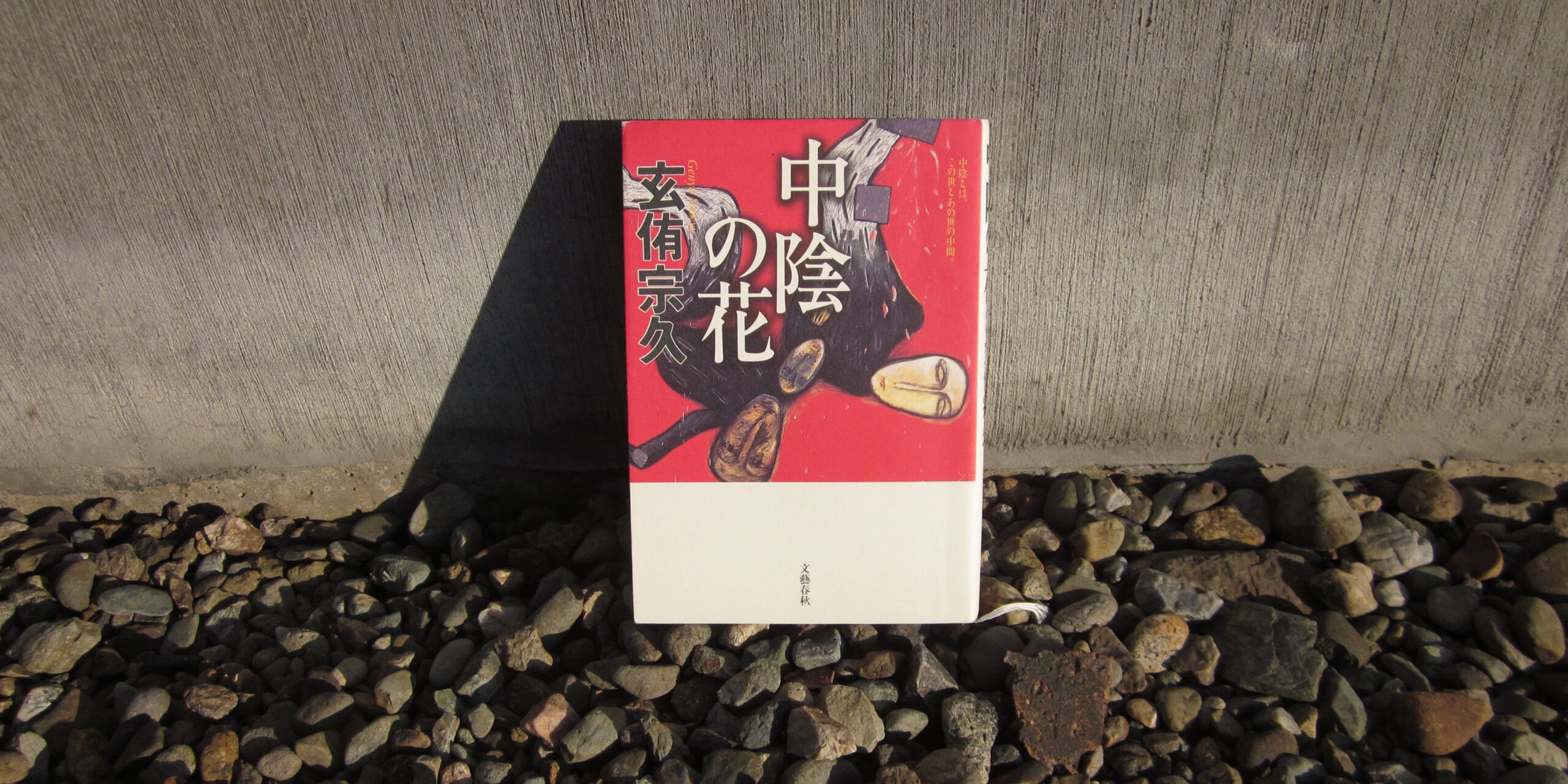 書評
書評