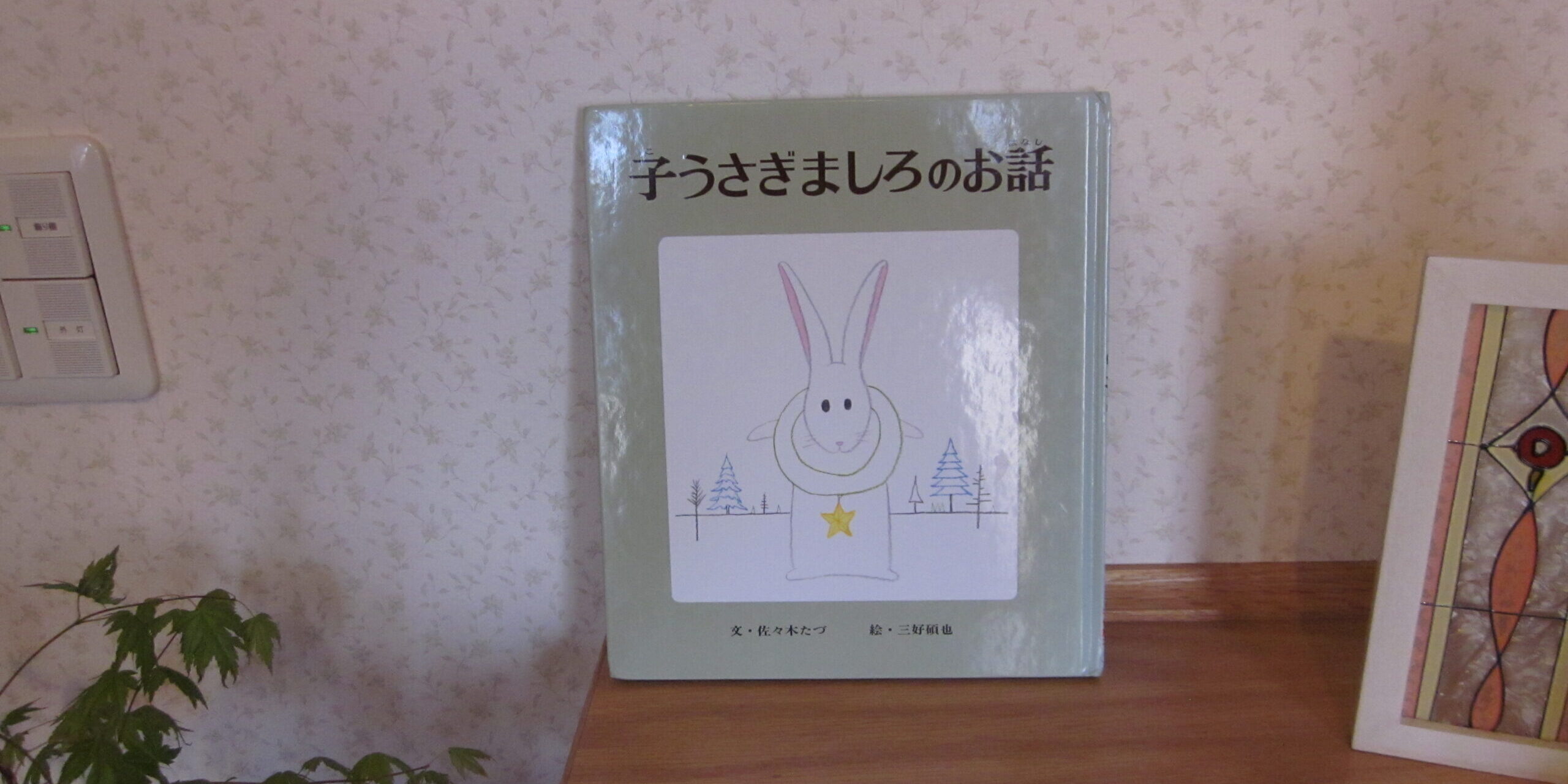これまでに書いてきた本の紹介を読んでくださった方々はもうお気づきのことと思いますが、私は気に入った本を何度も読み返すタイプの読書好きです。もちろん出版されたばかりの本も読みますが、このブログで本の紹介をすることになってからというもの、かつて読んだ本をさらにもう一度手に取る機会に恵まれました。その結果、ごく当たり前のことに改めて気がつかされました。それは、どの本にも読むたびに新しい発見があるということです。繰り返し読み込んだ上で本の紹介文を書くわけですから、基本的に同じ本を複数回読むことになります。そのなかで、最初に読んだときの印象と再読後の感じ方の間に最も大きな差異が生じた物語のひとつが、『切羽へ』です。この物語は第139回の直木賞を受賞していますから、世間的には高い評価を受けた作品です。しかし、およそ17年前に初めて読んだときには、私にはそれほどの作品だとは思えませんでした。よく、淡々と過ぎていく静かな日常を描いたなかに、登場人物の心の機微が鮮やかに描き出されているというような類の書評を目にします。女性作家の作品にこのような評価を得るものが多く見られるような印象がありますが、『切羽へ』の帯にはまさにそのような評が記されています。確かに、物語の語り手である主人公と、彼女が住む島にやって来た男との関係性にはこの評の文句があてはまるかもしれません。しかし、その他の登場人物たちの行動はそれなりに派手で、帯に記された評の通りだとはとても言い難いと感じたのです。物語の中核にあるはずの、主人公と島にやって来た男との関係性の静けさと、彼らを取り巻く人々の騒々しさに強いギャップを感じたのです。私自身の文章を読み解く力の不足を棚に上げながらも、『切羽へ』からはまとまりに欠けた作品であるとの印象を受けたことを覚えています。
しかし最近になって久しぶりに再読したところ、その印象に大きな変化が生じました。主人公と、彼女を取り巻く人々との関係性が実に巧みに描かれていることに改めて気づかされたのです。例えば主人公の母親について。タイトルにある「切羽」とは、「トンネルを掘っていくいちばん先」を意味します。あるとき、母親が父親の誕生日に木彫りのマリア像を贈ります。その像をどこで見つけて来たのかと父親がたずねると、母親は「切羽までどんどん歩いていくとたい」と答えます。また、主人公が男と二人で廃墟のベランダに立って話をする場面でも同様に、彼女の母の謎めいた行動が描かれています。廃墟のベランダに立ちながら、そこから見える、以前は坑道として掘り進められていたトンネルに向けて、主人公が指を差します。「いつか、母があの中で、十字架を拾ってきたとですよ」という台詞に続いて、「綺麗か、めずらしかものやった。こがんものばどがんして見つけてくるとかねと父が驚いて、そしたら母は、切羽まで歩いていくとたい、と自慢した」と言います。このふたつの場面は、主人公の母が「切羽」で男との逢瀬に興じていたことを暗示しているように思えるのです。他の登場人物についても同様に、少しずつ物語の主題に絡む経験が語られていることに気がついたとき、私は改めてこの物語の奥行きの深さに面白さを感じることができたのです。皆さんにもぜひご一読いただきたい作品です。
冒頭に書いたような、他者に対する感謝の気持ちは積極的に口にして、相手に伝えるべきものだと私は思っています。いくら心の中で念じてみても、言葉や文字に起こさなければ相手に伝わるはずなどありません。相手にとって嬉しいはずの想いなら、どんどん伝えてみてください。きっとその人との間に、今よりももっと深い絆を結ぶことができるはずです。しかしその反面、人には誰にでも決して口にしてはならない、隠し通さなければならない想いがあります。相手をむやみに戸惑わせ、悲しませるだけの想いなら、いっそ闇に葬ってしまうべきなのです。『切羽へ』の主人公は、まさにこのことを実践します。「身支度をすませておもてに出た。クロッカスの芽が出はじめていた。そのそばの土を少し掘り、小さな木切れのクルスを埋め」て、自らの想いを封印するのです。さあ、闇に葬りたい過去をお持ちのみなさん。この物語の主人公に倣って、因縁の品を土に埋めることで過去を封印してみてはいかがでしょうか。あっ、自然に還らないものを埋めてはいけませんよ。それは環境破壊というものですから。
32.『切羽へ』 井上荒野著 新潮社 2008年9月15日4刷
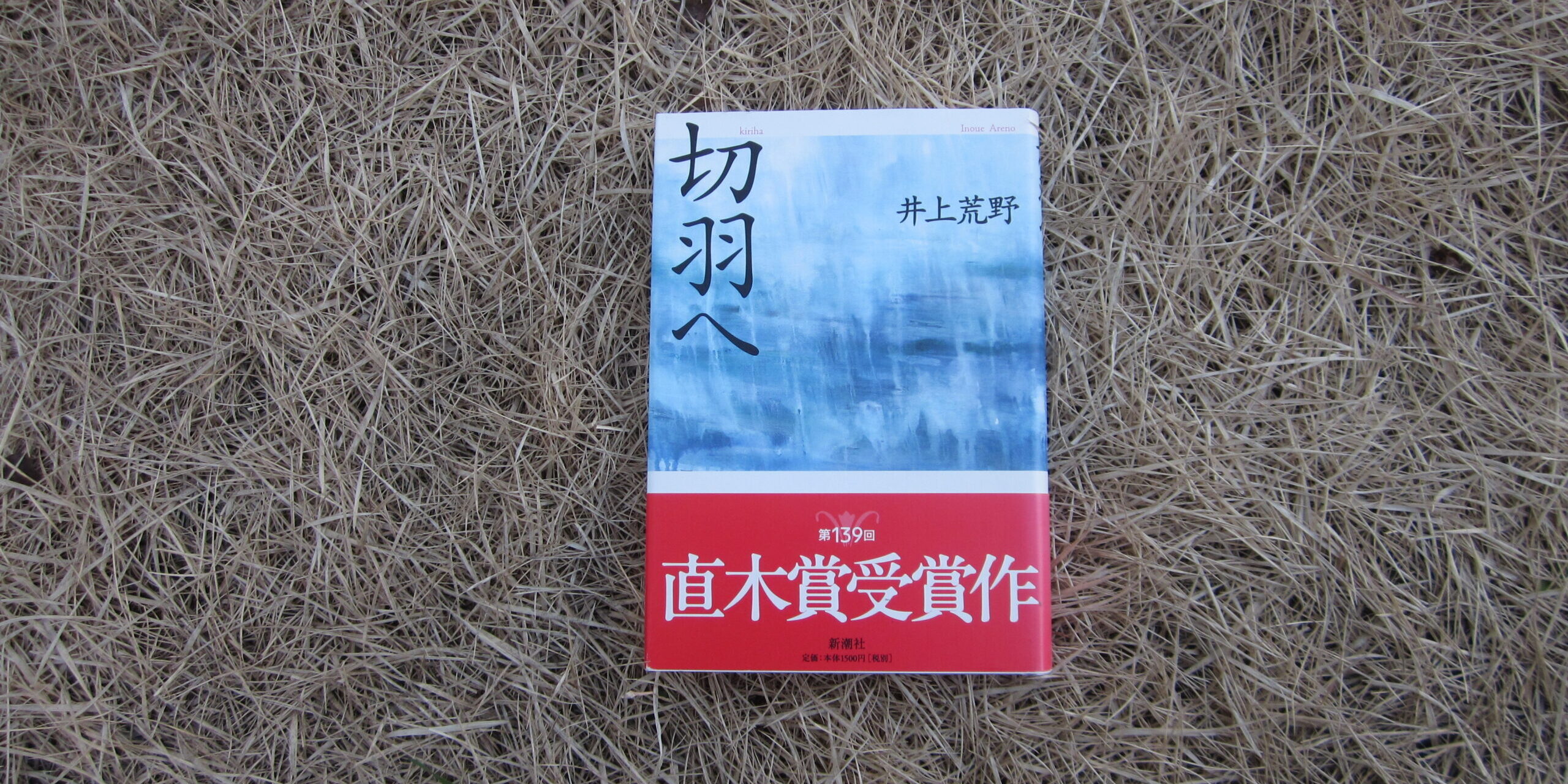 書評
書評