夏休みだ。職員室には柏木のほかに数人の教師がいるだけだった。
四人が職員室に入ってきたことに気がついた柏木は、右手首を上下にぱたぱたと動かした。どこか人を食ったような手招きに誘われるまま、私たち四人は彼のもとに歩いた。柏木はつと立ち上がり、職員室の奥へと歩いた。私たちはその後ろに従って、例の部屋に足を踏み入れた。
「どこでもいいから座れ。初日に限りびっくりどっきり大サービスで、お茶でも淹れてやろう」
柏木は目一杯恩着せがましくそう言うと、職員室内の流し台に向かった。
四人はそれぞれが立っていた場所に最も近い位置に席を占め、どことなく落ち着かないながらも各自鞄からもぞもぞと教材を取り出した。テキスト類を広げて間もなく、柏木がお茶を入れた紙コップを四つ、プラスチック製のバインダーの上にのせて運んできた。白い紙コップは、学校祭のときに開いた模擬店で使った分の残りだろう。
柏木は学校の名前が背中に入ったTシャツを着ていた。髪が濡れていた。
「先生、部活だったんですか?」
誠が話を切り出した。
柏木の身体全体から、わずかに埃くさいような汗くさいような、懐かしい体育館の匂いがした。
「うん、午前中な。夏休み中は徹底的に走り込むメニューを組んでるんだ。体育館の窓を全部閉め切って、夏の暑さを利用してわざと過酷な環境を作って。今のうちに暑さ対策をしておかないと、試合でバテるから」
空いた席に腰を下ろし、再び読み始めようと本を開きかけた柏木は、誠に対して視線を上げもせずにそう答えた。
「おかげでこっちもサウナみたいなところに三時間もいる羽目になるけど、辛いのは実際に動き回ってる生徒たちだからな。俺は我慢して付き合ってやんなくちゃ」
部活に未練があるわけではないが、参加している生徒たちを私は羨ましく思う。実現しようと思えば毎日、健康的な汗をかきながら何らかの達成感を得ることができる。それは何も部活動に参加する生徒に限って得られるものではない。しかし、運動に関するものであれば効果が単純で明快だ。その明るさが、今となっては懐かしい。
「先生も一緒に動いたんですか?」
今度は哲也が口を開いた。
「ああ、できるだけそうするようにはしてる。三十半ばのおじさんだけどな。そうすると、生徒も少しはやる気が出るみたいなんだ。それから、生徒のプレーの長所や短所が分かるようになる」
何となく、皆が「へー」という顔になっている。
「他には何か、気をつけて指導にあたっているようなことはありますか?」
「あるよ。たくさんある」
「例えば何ですか?」
「おいおい、何だかいきなり質問攻めだな」
柏木は眉間に皺を寄せた。皆、ハッと我に返ったように口をつぐんだ。柏木は私たち生徒のその様子を見て、かえって申し訳なく思ったのかもしれない。面倒臭いからひとつだけなと前置きしてから、質問への答えを話し出した。
「例えば、目線の高さにはいつも気をつけている。きちんと伝えたいと思うときには、相手の目線の高さに合わせるようにしている。試合中であれば選手を椅子に座らせて、その高さに自分の目線の高さに合わせるために、俺はひざまずく。そうした方が次にやってもらいたいプレーを選手に理解させやすい。でも、相手を叱るような場合は別だ。敢えて上から話をしなけらばならないときもある。相手の目線に立ってやるべきとそうでないときのメリハリをつけなくちゃならないんだ」
皆、黙ってうなづいた。
『明日の私』第6章「馬鹿」(3)
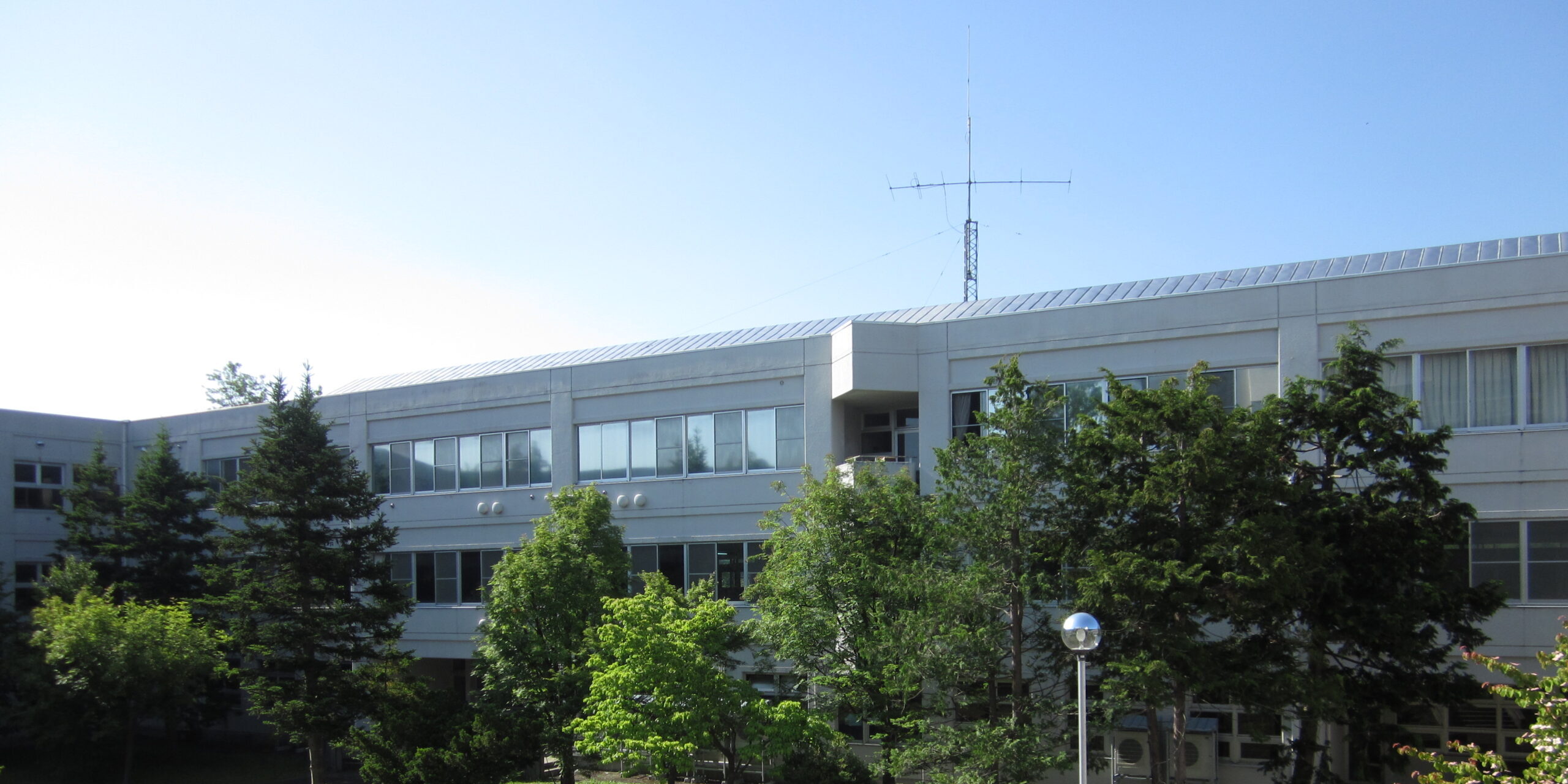 『明日の私』
『明日の私』
