 『永遠の花嫁』
『永遠の花嫁』 『永遠の花嫁』第二章「粉雪」B5
◆ 二月二十一日、火曜日の午後。桜田と山脇は、川村真理亜と椿が住んでいたアパートを訪ねた。そこに、いるはずのない人間が現れた。 つい前日に話を聞きに行った相手だ。別れてからまだ二十四時間も経っていない。倉科がその場に足を運んでいることの違和...
 『永遠の花嫁』
『永遠の花嫁』  『永遠の花嫁』
『永遠の花嫁』  『永遠の花嫁』
『永遠の花嫁』  『永遠の花嫁』
『永遠の花嫁』  『永遠の花嫁』
『永遠の花嫁』  『永遠の花嫁』
『永遠の花嫁』  『永遠の花嫁』
『永遠の花嫁』 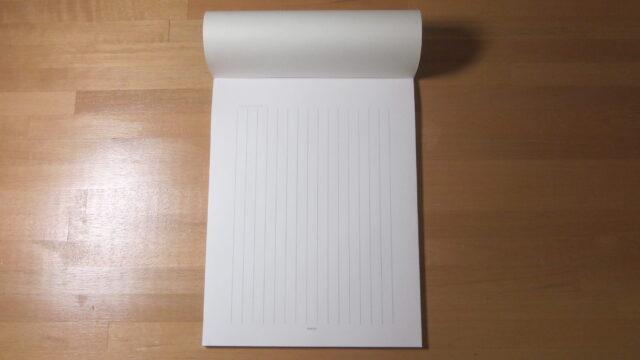 『永遠の花嫁』
『永遠の花嫁』  『永遠の花嫁』
『永遠の花嫁』  『永遠の花嫁』
『永遠の花嫁』